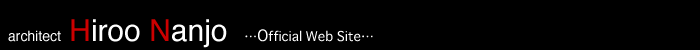 私の主張 |
|
| 建築家は街を美しくできるか? JIA会報「建築家」への書き下ろし未掲載原稿 |
|
| はじめに 都市再生が政府の基本政策とされる時代になった。不良債権処理も地方分権も、現在の都市のあり方を見直すことで活路を見いだせるのではないかと国民も期待を寄せている。 都市の環境、とりわけ住生活環境の遅れは、海外の事例を持ち出すまでもなく目に余るものがある。いつの間にそれほどまでに我が国の都市は不都合なものと成り下がってしまったのか。衣食住のうち、衣と食についてはつい先頃まで国民が享受していた経済繁栄で、贅沢といえる水準に達した。しかしその経済をもってしても住には手が届かなかった。それどころか不動産価格の狂乱により、人々の住への識別眼がすっかり狂ってしまった。 |
|
 [美しいロンドンの街並み] |
その間、建築家の多くは狂乱のさなかにいて企画や設計に関わっていた。未曾有の労力と資金とが投入された結果として、巨大な建築群が続々とその姿を見せはじめているが、その結果我が国の街は美しくなったといえるのだろうか。 6〜70年代には多くの建築家が都市を語っていた。先進国のように立派で近代的な、そしてたぶん美しい都市をつくりあげることが建築家の使命であると考えていた時期が確かにあった。しかし建築家は都市との戦いには活路を見出すことができず、次第に全体としての都市からは逃避し、個としての建築に関心を集中するようになっていった。 建築家は如何にこの街を美しくつくり直すことができるか、そのために建築家は何をすべきか。新世紀を迎えたいま、改めて建築家のまちづくりへの取り組みについて、考えてみたい。 |
 [典型的な郊外住宅地] |
まちづくりといえづくり |
 [美しいデュッセルドルフの運河のある街並み] |
公共空間への取組 建築家と都市計画家との違いを語るに、建築家が性善説にたつのに対して都市計画家は性悪説にたつという説明は説得力がある。建築家は自ら善人であると確信しているから建築基準法も都市計画法も創造行為を阻害するものと受け止めるが、建築家(敢えてけんちくやと呼ぶ)の多くが悪人であるとする都市計画家の立場からはもっと厳しく取り締まれということになる。 礼儀作法をわきまえない建築には、それを覆い隠す緑をもって対抗せよ。故にもっと街に緑をと叫ぶプランナーに建築家はどう応えるのか。たしかに醜悪な環境も年月を経て立派な緑で覆われたとき、すばらしいまちなみが実現する。緑溢れる美しい街並みこそが、いかなる建築単体の独創性にも優れて、真の豊かさをもたらすというのであれば、我々建築家はなぜ街路、広場公園、緑地づくりに立ち向かわないのか。 空洞化に苦しむ地方の都市は、美術館や図書館のようなハコモノではなく、都市再生の処方箋を必要としているのに、建築家はなぜ、そうした街の活性化に取り組まないのか。 現代の都市生活では、鉄道駅や空港など公共交通空間のデザインも、不特定多数の市民にとって日常活動のなかでの大変重要な要素である。であるならば建築家はなぜ、そうした公共空間のデザインに積極的に参加しようとしないのか。 |
 [ウェルシティ横須賀] |
大規模都市開発 湾岸副都心、汐留開発、六本木開発など、大規模な都市開発が東京のまちに完成しつつある。こうした大規模開発は、都市計画が先行し、設計建設段階でも土木から建築にいたる様々な空間デザイン領域が複雑に絡んだ総合的なまちづくりであり、既成の都市に対するインパクトが大きいが、ここでも建築家の存在感は少ない。 むしろこうした大規模開発に対しては、批判的な立場で発言する建築家が多い。であるならば建築家はなぜ、こうした大規模開発の現場に飛びこみ、自らの感性をもって開発の在りようを変えようとしないのか。批判的評論を後目に着々とこれらの開発は竣工を迎え、結局市民が多くの影響を受ける。かつて欧米の建築家たちは都市の開発の方向性に関し発言し、影響力をもっていた。我が国のニュータウン建設や大規模都市開発に建築家の名前を見るることは希である。 |
 [パリのオルセー美術館]
[パリのオルセー美術館]短絡的な経済効率追求が優先し、解体新築が正当化されることが多い中で、 スクラップ&ビルドに終止符をうち、まちの個性や人々のメモリーを大切にしていく事で、アイデンティティの高い固有のまちづくりを行おうとする動きが根をはりつつある。建築物や街並み景観などの保存再生がひとつの文化として市民権を得たと言えよう。
どちらかと言えば取り壊す側にいた建築家が、まちづくりという文化としての建築運動にあって、むしろ保存再生する側にたつ場面が多くなってきた。欧州の成熟した都市社会ではもはや当たり前とされる保存再生によるサステイナブルなデザインが、ようやく我が国でも表舞台に名乗りを上げたといえる。
これからは保存再生を難しくしている建築基準法の諸規定の見直しや、各種補助制度などの導入など、専門家としての知識と経験を、保存再生の促進に傾注することが期待される。

[エムシャーパークの環境建築]
都市は地球という大きなエコロジー体系に存続する。となれば一つ一つの建築という行為において、地球温暖化やヒートアイランドなどへの対策が必要であり、省エネルギーやリサイクルにも配慮したサステイナビリティの高い建築が求められている。
こうした環境への配慮はデザインの手法としても定着しつつある。屋上緑化や壁面緑化をはじめとして、太陽光発電や省エネルギー対応などが、建築の形態やデザインにまで大きく影響するようになった。
建築の規模が大きくなればそれだけ環境への影響も大きくなる。したがって環境への取り組みは、都市スケールでの対応が求められる傾向にあり、そこではハイテク中心の既成の枠組みを超えて建築家の自由な発想が期待される。
都市再生の実現に向けて、各方面の動きが活発化している。都市計画法と建築基準法の改正が施行された。総合設計制度の運用も大きく変わることになった。規制緩和への待望論が主流だが、性善説で本当に目的が達成できるだろうか。
市民参加によるまちづくりはもはや常識となり、建築家以外の多くの人々がまちづくりに立ち上がりつつある。建築家はそのなかで専門家として大きな期待を背負っている。
美しい街づくり、快適な都市づくりは、結局のところ市民の自覚によって実現する。市民の意識が高まるにつれて、各地域に専門家が必要となってくるはずだ。そのとき建築家は、あたかも町医者のように職能人として機能しなくてはならない。